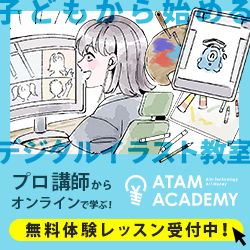当ブログでは、ビジネスシーンで“誰でも・手軽に使える”デザインノウハウ・テクニックをお伝えしています。
今回はプレゼン用のパワーポイント資料のレイアウトについて。スライドを作っていると、よく「レイアウトに迷ってしまう…」なんて声をよく聞きますが、そんな時は「レイアウトのパターン」に当てはめてしまうのがおすすめです。
今回は、企業の資料デザイン研修に講師として登壇することも多いデザイナーの筆者が、「パワポ資料のおすすめレイアウトパターン」をご紹介します。日頃プレゼン資料などを作ることが多い方の参考になれば幸いです。
- おすすめのスライドタイトルの位置
- おすすめのスライドレイアウトパターン3つ
- 株式会社トリッジ代表取締役 / デザイナー / コンテンツディレクター
- グラフィック・WEBデザインやオウンドメディアの運営サポート・ディレクションを手掛けつつ、パワポ資料作成の研修講師兼アドバイザーとしても活動中。パワーポイント資料作成の企業研修実績も多数(延べ150社以上、2,000人以上にレクチャー)。著書に『ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識』(株式会社インプレス発行)がある。
スライドのレイアウトに迷ったら「パターン」に当てはめればOK
パワーポイントでプレゼン資料などを作っていると、「スライドをどのようにレイアウトしたらいいか迷ってしまう…」ということはありませんか?
筆者は企業さんの資料デザイン研修で講師として登壇する機会も多いのですが、研修参加者さんからそういった声を非常によく聞きます。
パワポはデザインの自由度が高いので、確かにレイアウトに迷うこともあるかもしれません。そんな時は「レイアウトのパターン」をいくつか覚えておくのがおすすめです。
レイアウトのパターンというのは、要は「ひな型」ですね。パワポのレイアウトも「ひな型化」してしまえば、迷うことも減りますし、時短にもつながります。
以下の項より、スライドレイアウトのパターン化について整理していきます。
スライドのレイアウトをパターン化(ひな型化)するメリット
まずはスライドのレイアウトをパターン化(ひな型化)するメリットをざっくりまとめておきます。
パワーポイントはプレゼン資料を作るときなどに必須のツール。レイアウトは基本的に自由で、正解というものはないですし、こうしたらいけないということも基本的にはありません。
そのため、逆に自由度が高すぎて、レイアウトに迷ってしまうわけですね。そんな時「パワポのレイアウトのパターン(ひな型)」をいくつか持っておくのがお勧め。レイアウトをパターン化するメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
- 自由度が高過ぎるスライドのレイアウトで迷わなくなる
- 迷わないから、全体の作業時間の時短につながる
- パターン化されることで「どこに・何が書かれているか」がわかりやすくなる
パターン化し、それに当てはめて作ることができるようなれば、いちいちレイアウトに迷うことがなくなり、全体の作業時間の時短につなげることができます。
また、③の「どこに・何が書かれているかがわかりやすくなる」という点も大きなメリットです。ある程度資料全体のレイアウトがパターン化されると、聴衆の方々も「どこに何が書かれているのか」が見ているうちに刷り込まれてきます。たとえば「キーフレーズはいつも右側に書かれてるから、そこは見逃さないようにしよう」と無意識に注意深く見るようになったり。
そうすると、資料全体がわかりやすく感じるようになるわけです。パワポ資料作成において、これらのメリットは結構大きいので、作業効率・わかりやすさの面において重要です。
スライドレイアウトのおすすめパターン(ひな型)
ここまでの内容で、レイアウトをパターン化することの重要性はある程度わかったかと思いますが、では具体的にどのようなパターンを覚えれば良いのでしょうか。たくさんあると、それこそ結局迷ってしまうことにつながるので、とりあえず覚えておくべきパターンは3つでOKです。
というのも、ビジネスシーンでよく使うプレゼン資料のレイアウトパターンとしては、3つほどあれば十分内容を伝えられることが多いからです。そのため3パターンをとりあえず覚えておきましょう。それぞれ見せ方のポイント等もあるので、併せて押さえておくのがお勧めです。
なお、全パターンに共通している「タイトル」については、先に解説しておきます。
共通:タイトルは「左上」に置く
![]()
- 平面のデザインの場合「左上から右下に向かって目線が動く」
- タイトルは資料の「道しるべ」。まず目に入る左上に置くのがベター。
タイトルの位置は、基本的には左上がベター。横書きの時に左から右に向けて書いていく文化圏の人の目は、基本的に平面のデザインにおいては「左上から右下に向かって目線が動いていく」という習性があります。これはZの法則と呼ばれ、以前当ブログの別記事でもご紹介しました。
その上で、タイトルは「このページでは何について話そうとしているのか」を伝える道しるべ役なので、まず目に入る左上においてあげるのがおすすめ。これはどのレイアウトの型においても共通しているので、まずはこの点を押さえておきましょう。これでもうタイトル位置で迷うことがなくなりました。
おすすめ①:上にキーメッセージ、下にビジュアル要素
![]()
- ベーシックなレイアウトで見慣れている
- 比較的横に長くなるグラフだとか表との相性がいい
1つめのおすすめレイアウトパターンは、タイトルのすぐ下のところに「1〜2行のキーメッセージ」を置いて、その下に大きくビジュアル要素(グラフ、図解、表)を配置するもの。よく見かけるベーシックなレイアウトになりますが、多くの人が見慣れたパターンになるので、使いやすくお勧めです。
このレイアウトパターンの場合、ビジュアル要素を置くデザインスペースが「大きな横長の長方形」のスペースになるので、比較的横に長くなるグラフや表との相性がいいという特徴があります。
ちなみにキーメッセージの位置については、一般的には「下に置くのはNG」という意見が多い印象がありますが(特にコンサル系の会社さんはキーメッセージは上に置くべき!というのを徹底していることが多い)、筆者個人の見解としては「上でも下でもOK」と考えています。
上にキーメッセージを配置するメリットとしては、「先に結論が伝えられてわかりやすいから」という点が考えられます。ただし、プレゼンの展開によっては先に結論を述べるよりも、データや図解などを示した上で、そこから得られる示唆・自身の見解をメッセージとして伝えた方が、よりわかりやすく感じるという展開もあるはず(プレゼンの演出上、先に結論を見せない方がいいケースなどもありますよね)。
そのためキーメッセージを下に置くというのも、伝えたい内容やプレゼンの展開によってはアリだと筆者は考えています。
要は使い分けが肝心。「とにかく早く結論が知りたい!」というような方(たとえば役職の高い方々など)を相手にプレゼンするなら「上にキーメッセージ」を置いてあげればいいし、説明のプロセスや順序が大事な内容だったら、あえて「下にキーメッセージ」を置いてあげてもいいでしょう。
また、スクリーンに投影した時に、下にキーメッセージが書かれていると聴衆の方々が見づらい場合(たとえば「前の人の頭で文章が隠れて見えない!」など)が想定されそうなケースであれば、キーメッセージは上に置いてあげるのが無難です。うまく使い分けをしてみましょう。
おすすめ②:左にビジュアル要素、右にキーメッセージ
![]()
- 縦に長くなるグラフなどが見せやすい
- テキストも箇条書き等で縦にまとめやすい
データを示すグラフやイメージ画像などの「ビジュアルで伝える要素」を左側において、伝えたい主張だとか結論を右に配置してあげるパターンもおすすめです。
このレイアウトだと、縦に長くなるグラフなどが見せやすかったり、キーメッセージを書くスペースも縦に長く使えるようになるので、「簡単な説明→結論」のような見せ方もしやすくなります。
また、ポイントを箇条書きで端的にまとめてあげたりもしやすくなるので、「最後のまとめのスライド」などとの相性もいいでしょう。
このレイアウトパターンを使うときのポイントは、「左側にビジュアル要素、右側にメッセージを置く」という配置です。これは過去の記事でも触れていますが、人間の目線の動き・脳の情報処理の関係で、「ビジュアル要素は左側、テキスト情報は右側」にあった方が違和感なく見られるという傾向があります。
特に画像は目線をすごく奪いやすいため、それが右側に置かれていると、「まず目線のスタート位置が右にいき、そのあとテキストを見るために目線が左に動く」という、本来の目線の動きである「左から右へ」の流れと逆になってしまうことがあります。これによって見た目の違和感を無意識に感じてしまうことも。
そのため、「ビジュアル要素は左、キーメッセージを右」というレイアウトしてあげるのがお勧めです。このレイアウトパターンも意外と使いやすいので、ぜひ色々なパワーポイント資料で使ってみてください。
おすすめ③:テキストをど真ん中に置くだけ
![]()
- シンプルかつ大胆なレイアウトだからこそ、メッセージの重要性が際立つ
- 大きく場面転換するような時にも効果的
最後3つ目のおすすめは、スライドのど真ん中にテキストボックスで自身の主張やキーメッセージを書いてあげるだけという、めちゃくちゃシンプルなレイアウトパターン。このレイアウトの場合は、一番上のスライドタイトルすら外してしまっても構いません。
すごくシンプルかつ大胆なレイアウトだからこそ、書かれているメッセージの重要性が際立つレイアウトなので、よりメッセージを強く主張したい場面にお勧め。
また、プレゼンの中で大きく場面転換するような時に使うのも、効果的です。特にこのレイアウトは情報量をぎゅっと少なくすることができるので、余白がたっぷりとれて、見栄え的にもわかりやすくなります。
すでにお気づきかもしれませんが、このレイアウトパターンの肝は「余白」です。余白は情報を整理したり、要素を強調する効果を持っているので、レイアウトパターンにおいてもうまく活用してみましょう。
余白が持つ効果についてもっと詳しく知りたい方は、下の記事も併せて見てみてくださいね。
以上3つがおすすめのスライドレイアウトパターンです。3つともシンプルで使いやすいので、色々なプレゼン資料で試してみてください。
YouTubeで今回の記事の内容を見たい方はこちら
今回の内容を動画で見たい方は、当ブログ筆者がYouTubeチャンネル『ビズデザ』でも解説しているので、こちらも併せてご参考ください(チャンネル登録もしていただけると、中の人は飛び跳ねて喜ぶそうです)
まとめ:パワポ資料のレイアウトはパターンにハメるのが吉。3つだけ覚えてうまく使いまわそう。
今回はプレゼンで使うパワポ資料の「レイアウトパターン」について、お勧めをご紹介しました。
パワポ資料はレイアウトの自由度が“高過ぎる”ので、どんな配置にすればいいか迷ってしまうこともあると思いますが、そんな時は今回ご紹介したお勧めのレイアウトパターンに当てはめて作ってしまうのが◎。どれも多くのケースに対応できるパターンなので、ぜひ色々なプレゼン資料で使ってみてください。
使い回しをしていけば、資料作成の時短・効率化もグンッと進むこと間違いなしです。