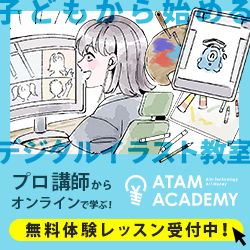当ブログでは、ビジネスシーンで作成する資料で“誰でも・手軽に使える”レイアウトノウハウ・テクニックをお伝えしています。
今回はビジネスシーンでのパワポ・プレゼン資料でつい使いがちな「カタカタ語」の使用についての内容です。
カタカナ語の使用は避けるべきなのか、それともある程度は許容すべきなのか、筆者の考えをまとめてみました。
日頃プレゼン資料を作ることが多い方の参考になれば幸いです。
- カタカナ語とは何か/li>
- カタカナ語を使用するときのポイント・注意点
- どのようなケースならカタカナ語が許容されるのか
- 株式会社トリッジ代表取締役 / デザイナー / コンテンツディレクター
- グラフィック・WEBデザインや自社で展開するオウンドメディアのディレクションを行いつつ、パワポ資料作成の研修講師兼アドバイザーとしても活動中。パワーポイント資料作成の企業研修実績も多数(延べ150社以上、2,000人以上にレクチャー)。著書に『ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識』(株式会社インプレス発行)がある。
カタカナ語とは?
「カタカナ語」という言葉は多くの方が聞いたことがあると思いますが、そもそもカタカナ語とは何を指すのでしょうか。簡単に言ってしまえば、カタカナ語とは「カタカナで表記される日本語」のこと。でも、これだとイマイチ意味合いがぼやっとしてますよね。
筆者は以前カタカナ語について調べたことがあるのですが、実のところカタカナ語の明確な定義は見つかりませんでした(単純に調査不足かもしれませんが…)。ただ、一般的に使われるケースを考えてみると、以下の2つに分類されるのではないかと思います。
- 主に欧米から日本にやってきた、カタカナで表記される「外来語」(例:ストレス、テーマ、コミュニケーション等)
- 英単語の意味を日本人が解釈して作り上げた「和製英語」(キャッチコピー、サラリーマン等)
普段このような2つの違いを意識しながら使い分けているという人は少ないと思いますが、日頃何気なく使っている言葉であることは間違いないでしょう。
プレゼン資料でのカタカナ語は使い分けが大事
そんなカタカナ語ですが、プレゼン資料では「カタカナ語は使わない方がいい」ということをよく耳にします。実際に筆者も以前はそう思っていて、筆者が登壇したパワーポイント資料作成研修でも「カタカナ語はなるべく避けましょう」ということをお伝えしていました。
ただ、最近は少し考え方が変わってきまして、カタカナ語は「ケースバイケースで使い分けをするのが大事」という結論に至っています。
どのような使い分け方なのか、この辺りを下に整理していきます。
カタカナ語を避けた方がいいケース:プレゼンの聞き手の属性がバラバラなとき
まずカタカナ語の使用をなるべく避けた方がいいケースとしては、「プレゼンの聞き手の属性がバラバラなとき」です。
プレゼンシーンによって、聴衆の方々の属性(年代、性別、関心ごと、所属業界、所有している前提知識など)がバラバラなケースがありますよね。たとえば「社会人のためにビジネススキルセミナー」などと銘打ったセミナーだと、扱うテーマが広くなるため、参加者の属性もかなり幅広くなります。そのような時は、極力“誰でも聞いてわかる”言葉で表現してあげた方がベターでしょう。
特に特定の業界の専門用語や、“なんとなく響きがかっこいいもの”などは避けた方が無難です。注意した方がいいカタカナ語の例としては、以下のものが挙げられます。言い換え例も併せて載せておくので、参考にしてみてください。
- コミット → 目標に責任を持つ
- アサイン → 割り当てる/任命する
- アジェンダ → 予定表/議題
- ディビジョン → 部署
- モニタリング → 点検
- エスカレーション → 上位への伝達
- ハレーション → 悪影響を及ぼす
- コストリダクション → 費用削減
- コンセンサス → 全員の意見の一致
- キャッチアップ → 追いつく
- シルバーエイジ → 高齢者
- ペライチ → 紙一枚の
カタカナ語を使用してもいいケース:プレゼンの聞き手の属性が絞られている時
一方で、プレゼンの聞き手の属性が絞られているようなケースというのもありますよね。たとえば先ほどのセミナーの例でも、「マーケティング担当者・マーケター限定セミナー」などのように特定の分野に特化した内容だったら、必ずマーケティング担当者しか参加しませんし、それぞれが所有している前提知識などもある程度重なっているはず。
そのような時は、筆者としては“ある程度の専門カタカナ用語”は使ってもOKだと考えています。なぜなら、こういった特定の分野に特化した内容のプレゼンだった場合、わかりやすさはもちろんのこと、プレゼンの「世界観」も重要だからです。
世界観とは、つまり“その世界らしさを感じさせてくれるモノや言葉”。たとえばマーケティングの領域であれば、誰でもわかるからといって「見込み客」という言葉を使うよりも、「リード」という言葉で表現した方が、よりマーケティングの領域らしい世界観を感じることができますよね。
普段から専門領域に触れている人の場合、見慣れている専門的なカタカナ用語などが使われていた方が(=世界観が表現されている方が)、ちょっとしたニュアンスや意味合いの違いを素早く感じとることができるので、より内容のイメージがしやすくなったり、より内容に没入しやすくなるはず。そのため、プレゼンの聞き手の属性が絞られている時に限っては、“ある程度の専門カタカナ用語”は使ってもOKと筆者は考えています。
また、ある程度専門カタカナ用語が理解できる人の集まりであれば、カタカナ用語を使った方が細かな説明を省くこともできます。たとえばマーケティングの領域においては「ロングテール」というカタカナ用語は基礎的な言葉ですが、これをわざわざ別の“誰でもわかる言葉”に置き換えようとしたら、「ニッチで販売機会の少ない商品を大量に取りそろえることで、全体として売り上げを大きくすること」などのように説明がすごく長くなってしまいます。
これではプレゼンが逆にわかりづらくなったり、時間がかかったりしてしまうので、やはり属性が絞られている場合(ある程度専門カタカナ用語が理解できる人が聞き手の場合)は、専門カタカナ用語を使用しても良いのではないでしょうか。
絶対に使ってはいけないカタカナ語:自社内でしか使っていないカタカナ用語・略称
ただ、プレゼンにおいて絶対に使ってはいけないカタカナ語というのも存在します。それは自分と近しい間柄の人との間でしか使っていないカタカナ用語や略称です。
特に日頃仲間内でしか通用しない略称などが「うっかりプレゼン資料に残っていた!」というケースも稀に見かけます。カタカナ略称は絶対に相手には伝わらないので、必ず使わないようにしましょう。
以上が筆者が考えるプレゼン資料におけるカタカナ語の使い分け方です。最終的にはケースバイケースになってしまうことも多いと思いますが、参考になれば幸いです。
まとめ:常に聴衆の方々の目線で
今回は、ビジネスシーンでのプレゼン資料でつい使いがちな「カタカタ語」の使用について、筆者の考えをまとめました。
当ブログでは一貫してお伝えしている通り、パワーポイント作りでは常に「聴衆の方々が見てわかりやすいか」を意識する必要があると思います。
カタカナ語の使い方も、日頃から「聴衆者目線」を意識しておくことが大切。言葉のひと言ひと言が資料のクオリティを左右するので、ぜひ意識しておきたいところです。